7月31日、日本一ソフトウェアより発売される風雨来記5。発売をされるのを機に、観光と下見として訪れてみようと思う。
舞台となる三重県は愛知県とは隣県ではあるものの、東三河からでは車でもそれなりに時間が掛かってしまう。そこで伊良湖のフェリーに乗り、三重県鳥羽市へと向かうこととした。
愛知県と三重県の重要なアクセス手段となる伊勢湾フェリー。愛知県の南端に暮らしている身としては非常にありがたい。
10月より料金改定にて上がるようだが、それでも旅客運賃は往復3770円は安いのではないかな。車の搭乗となるとそこそこの料金となるため、車は搭乗せず三重からは歩きと公共交通機関で行こうと思う。

三重県鳥羽市。フェリーより約1時間で到着。豊橋から伊良湖までも車で約1時間ほど。
早速、目に留まった噴水とイルカのオブジェクト。噴水の勢いと合わせて、まるで飛び跳ねているかのようだ。
鳥羽市には通称イルカ島(日向島)と呼ばれる島がある。鳥羽湾ではもしかしたら野生のイルカが見られるのかもしれない。

海を眺めていると、何だか凄そうな船が出航していた。船首の亀に乗った人物や乙姫らしき人物がおり、竜宮城をイメージした船のようである(よくよく見ると船に竜宮城と書かれている)
この船はどこへ向かうのか…。
同じ海を見ていても伊良湖や白谷とは変わった雰囲気を感じられる。

鳥羽といえば、伊勢湾フェリー乗り場のそばに鳥羽水族館がある。そこから国道を挟んだ向こう側に石垣と大きな家紋が見てとれる。
九鬼水軍を率いた九鬼嘉隆が築城した鳥羽城の跡地となっている場所である。
鳥羽湾に面しており、大手門が海側に設けられていた特徴的な城であった。今では国道を挟んでいるが、当時は四方を海に囲まれていたようだ。その構造から鳥羽の浮城とも呼ばれている。

城跡地の敷地内は現在は城山公園として整備されている。訪れた時期(5月)では小山の緑豊かな公園そのものであった。
のんびりと散策にはよさそうである。

公園からの眺めは良く、鳥羽湾を眺めることが出来る。眺めてみると様々な島があるようだ。
…眺めていると突然、オウッオウッと鳴き声が聞こえてきた。
アシカかな。鳥羽水族館でショーでもやっているのだろうか。

嘉隆桜。築城した九鬼嘉隆にちなんだ桜のようだ。
桜の季節でないものの、見頃となれば綺麗な桜と鳥羽湾を見ることが出来そうだ。

♡TOBAと書かれた面白いモニュメントを発見。
鳥羽湾の美しい景色と合わせて写真を撮ってみるのもいいのかもしれない。
鳥羽へ行ってきたとして記念に残るだろう。


公園として整備はされているものの、かつては城であったと思わせる石垣である。
がっちりと固めたような造りでなく、石の大きさもまばらで所々空間がある。そのまま石を乗せたような造りのようだ。
棚田のような形状をしている。石垣も復興したものだろうが、当時を再現しているのかもしれない。

開けた場所に着いた。鳥羽城の本丸跡地。かつて天守閣があったと思われる。
鳥羽城は天守閣は3層であり、屋根の構造から「望楼型(ぼうろうがた)」と呼ばれる古い型式の天守閣であったとされている。

本丸跡は隣接する鳥羽小学校の旧校舎の運動場として使われていたようだ。
鳥羽小学校の旧校舎は昭和初期に竣工した小学校であり、当時はまだ木造校舎が主流であった中、鉄筋コンクリートで建設された校舎となる。老朽化もあり、現在の校舎は別の場所へと変わっている。
こちらの旧校舎は日本の登録有形文化財として保存がされている。

屋外子局だろうか。本丸跡はちょうど小山の開けた場所となっているため、地震や津波による避難場所として設定されていてもおかしくはない。
錆びており建てられてからそれなりの年月が経っているのだろう。

所々見かける家紋。手裏剣のようなデザインと思っていたが、よく見ると黒い勾玉のような模様が三つに分かれている。
鳥羽城を築城した九鬼嘉隆の「左三つ巴」の家紋のようだ。
…ここで鳥羽城を築城した九鬼嘉隆(1542年~1600年)について軽く触れておこうと思う。

織田信長・豊臣秀吉の家臣
九鬼嘉隆は志摩国出身であり、九鬼氏は志摩十三地頭の一勢力であった。
国司の北畠氏に属していたが、後に他の地頭たちと対立。地頭たちは北畠の支援を受けており、嘉隆は居城を攻められ敗北。故郷を追われた。
その後、嘉隆は織田信長が勢力を拡大すると信長に仕えるようになる。
志摩国平定において信長は嘉隆の因縁の北畠の本拠地大河内城へ攻め入るも籠城され、長期戦にとなる。信長に仕えた嘉隆は要衝であった大淀城を海上より攻略した。
長期戦の末、信長と北畠の戦いは最終的に和睦という形で終結。この戦いにより嘉隆も信長に水軍の才能を評価したとされている。
また、1576年の織田水軍と毛利水軍の木津川口の戦いでは、毛利水軍の火矢に織田水軍は打撃を被り敗北を喫してしまう。そこで信長は嘉隆に燃えない船の建造を命じ、嘉隆は鉄甲船の建造を取り組む。2年後の第二次木津川口の戦いでは外装を鉄板に覆った鉄甲船は火矢では通じず、毛利水軍(中核は村上水軍)を打ち破ることに成功する。
本能寺の変後より豊臣秀吉に仕えている。引き続き水軍の将として朝鮮出兵でも活躍している。
そんな折、1594年に鳥羽城を築城した。
最期
1600年の関ケ原の戦いでは、嘉隆は西軍(石田三成側)につき、嘉隆の次男である九鬼守隆(1573年~1632年)は東軍(徳川家康側)につくように親子で敵味方に分かれることとなった(一説によるとどちらが勝っても九鬼家を存続するためと言われている)

西軍が敗北をすると、嘉隆は鳥羽市の島である答志島(とうしじま)に逃れる。守隆は家康に父の助命嘆願をし、それに家康も許したものの、その知らせが嘉隆に届く前に嘉隆は自害を果たしてしまったとのことだ。
⋯栄枯盛衰のような人生を辿った九鬼嘉隆。
風雨来記5でも登場人物の推しの武将であり、おそらく九鬼嘉隆に纏わるスポットを巡る話となるのではないかと思われる。鳥羽城以外にもどのようなスポットを巡っていくのか見ていきたい。
⋯ここ鳥羽城跡がゲームのスポットとして登場するのか分からないが。
ちなみに、余談となるが次男の守隆は愛知県田原市にも墓があるようだ。
守隆の娘が田原藩の2代目藩主・戸田忠能の正室としたことから、戸田家の菩提寺の長興寺に守隆の墓も建造されている。
九鬼氏が地元とも縁があるのはちょっと驚きであった。

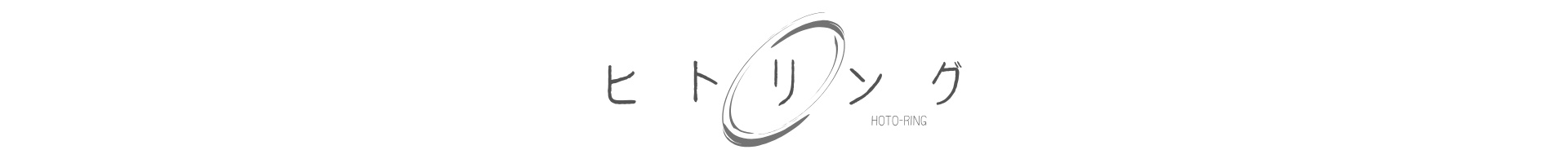





コメント