
風雨来記5にて、三重県神島にある観測所を訪れた際にこのような文面があった。
伊良湖には射場(伊良湖試験場)があり、そこから発射される砲弾を各地にある観測所にて着弾の確認を行っていた。伊良湖から距離が近い神島においても監的哨が存在している。
六階建と電信所

田原市においても戦争に関わる遺構は残っており、その中でも一際目立つのが住宅や畑の中に存在する気象塔兼展望塔(通称:六階建)がある。

六階建の傍には説明書きがされている看板がある。高さ19mもあり、射場から放たれた砲弾の弾道や風速・風向きなどの観測を行っていたとされる。同時に名前の通り、気象観測もされていたようだ。
当時の写真では線路があり、砲弾の運搬など行っていたのだろうか。
1930年完成とされている。戦間期の最中であり、日本はその後の満州事変や国際連盟の脱退、日中戦争を経て太平洋戦争へと続いていく。その時代の中で、射場と併せての重要な施設だったのかもしれない。
説明書きにもある通り、許可なく入ることは出来ない。


鉄筋コンクリート造りのようだが、外壁は剥がれ鉄筋がむき出しになっている。もうじき100年となるため致し方ないが、全体的な外見はそのままであるため、よほど丈夫な造りだったのであろう。

外から覗く階段。まだまだ状態は保たれている。

近くにある二階建ての建物は無線電信所。各地に点在していた観測所より無線連絡を行っていた場所のようだ。
こちらは草の蔦などがからまり、本来の遺構のような姿となっている。中には農業資材なのか分からないが様々な物が置かれている。

…そういえば、何故伊良湖を射場として選ばれたのであろうか。
調べてみると、畑などの農耕地が多い田原市であるが山が少なく、着弾の確認がしやすかったことや、砲弾の発射から確認までの距離を測るための広さも十分であったこと、また土地の買収しやすかったことも選ばれた理由のようだ。
しかし、当時住んでいた人たちは立ち退きがあったようで、伊良湖村の人たちは大規模な移転を余儀なくされてしまった歴史もある。
福江観測所
一色観所や、外浜観測所など田原市にも観測所が点在している。
その中で、福江観測所へ訪れてみた。

地元の高校裏手の小山の藪の中にある。少し訪れるのに苦労をした。

レンガ造りの竈のような構造に歴史を感じさせる。藪の中にあり観測所という名残は見られないが、小山ということもありかつては確認しやすかったのかもしれない。

中には木製の椅子が隅にぽつんと置かれているのみ。木陰で日の光があまり入らずなんとも哀愁が漂う雰囲気となっている。

小さい階段の上がおそらく展望台となる。コンクリートで出来た何かの物体が残されているが、これは一体何に使われていたのだろうか。

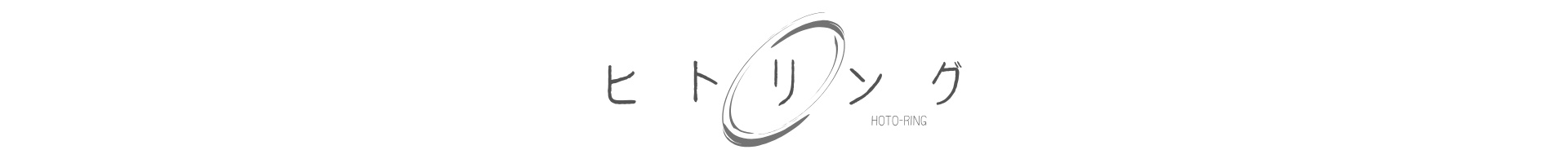


コメント